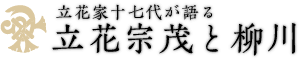皇族や華族は鳥類や昆虫などを研究対象とし、政治とは無縁の学問を指向したと言われています。(『科学朝日』編『殿様生物学の系譜』朝日新聞社 1991年)。農学を修め、その成果を活かすべく沖端川の畔に農事試験場を築いた明治期の立花家の当主寛治の活動もそのような文脈で捉えられてもおかしくはありません。しかし結論から述べますと、立花寛治の農学は、「殿様生物学」ではなく同時代の政治を意識したものと考えられます。
立花寛治(幼名徑丸)は柳河藩最後の藩主鑑寛の次男として安政4年9月5日に御花畠で生まれます。一時期、一門の家へ養子に出されますが、兄鑑良の急逝により明治7年に生家に戻され、同年12月に父の隠居にともない僅か18才にして立花家の家督を継ぐことになりました。後に農事試験場を築くこととなりますが、寛治は最初からそのような構想を抱いていたわけではありません。当初は柳川の農業に限らず、日本国内の物産を興隆させることを構想していました。ではいつ頃から寛治は農学を志望するようになったのでしょうか。この点についてははっきりとはわかりませせんが、明治12年の秋ころにはそのような意志があったことは確認できます。そして翌13年1月に当時、著名な老農であった津田仙が開いた学農社農学校の門を叩きました。
しかし寛治の回顧によれば、学農社の授業は机上の学問を重視しており、実践面が軽視されていると感じたとあります。そのため、彼は東京の立花家邸内を造成して、簡易の試験場を設けて自ら試作を行いました。しかしその面積は広くはなく、米の試作もできなかったため、寛治は不満を抱き、より広大な場所を探すようになりました。もっとも彼の周囲にいた親族や相談人たちは、立花家の財政の規模から判断すると大規模な事業は難しいので、農商務省の役人となるか、あるいは大日本農会という民間の農業団体で活躍して欲しいと願っていました。実際に寛治は彼らの意向に添う形で、一時期、大日本農会が経営する三田育種場の場長補となっています。
このように寛治の就職問題は円満な形で解決したかのように見えますが、実は彼自身は農事試験場建設に強くこだわっていました。これには深い理由がありました。そもそも寛治は、華族が模範とすべきはイギリス貴族であると考えていました。そして明治23年に国会の開設が決まって以降、華族はイギリス貴族と同様に上院に議席を持って国家に貢献しなければならず、もしそれが叶わないのならば、別な形でその目的を果たすべきであるという見方を示しています。そうした華族としての強い使命感が彼を農事試験場建設へ駆り立てたと言えるでしょう。その結果、彼自身の私財をなげうって、山門郡中山村に大規模な農事試験場を完成させました。
中山農事試験場では、数多くの果実や野菜の試験を行い、その結果を出版物として刊行したり、あるいは近隣の篤志家たちを集めて種苗交換会や品評会などを開催しました。そのような過程を通じて、全国に広まったものに、今日、早生品種としては最も流通している宮川温州みかんが挙げられます。寛治は昭和4年2月5日に71年の生涯を閉じるまで中山農事試験場(後に立花家農場)の経営に身を捧げました。 |